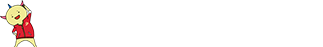福井県民の飲酒の状況
皆さんはどのくらいのアルコールを摂取していますか?
福井県民は、生活習慣病のリスクを高める量(1日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上)を摂取している方が、男性で12.1%、女性で5.9%います。
飲酒による健康リスク
生活習慣病のリスクを高める量
厚生労働省の健康日本21において、1日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上とされています。
お酒に含まれる純アルコール量は、この式で求めることができます。
純アルコール量(g)=摂取量(ml)×アルコ ール濃度(度数/100)×0.8(アルコールの比重)

また、厚生労働省が作成した「アルコールウォッチ」では、飲んだお酒の種類と量を入力することで、純アルコール量と分解時間を把握することができます。

疾病発症等のリスク
①急性アルコール中毒…急激に多量のアルコールを摂取すると、意識レベルが低下し、嘔吐、呼吸状態が悪化するなど危険な状態になります。
②肝疾患…はじめに起こるのはアルコール性脂肪肝で、飲みすぎると発生します。一部の人はアルコール性肝炎になり、まれに重症化して死亡することもあります。わが国では、明らかなアルコール性肝炎の既往なしに肝臓が線維化して硬くなる肝線維症が多く、さらに飲み続けると肝硬変へと進行します。
③アルコール依存症…大量のお酒を長期にわたって飲み続けることが主な原因で発症する精神疾患の一つです。お酒をやめたくてもやめることができない、飲む量をコントロールできない等の症状により、仕事や家庭など生活面にも支障が出てくることがあります。
年齢や性別等の違いによる影響
10代から20代は、脳の発達の途中であり、多量の飲酒によって脳の機能が低下するほか、健康問題のリスクが高まる可能性があります。高齢になると認知症の発症の可能性が高まり、飲酒による転倒・骨折、筋肉の現象の危険性が高まります。
女性は、男性に比べて分解できるアルコール量が少なく、エストロゲン(女性ホルモンの一種)等のはたらきでアルコールが影響を受けやすいため、少ない量かつ短い期間での飲酒でアルコール関連肝硬変になる場合があります。
アルコールを分解する酵素の働きが弱い人は、飲酒により、顔が赤くなったり、動機や吐き気がする状態(フラッシング反応)になることがあります。日本では、この反応を起こす方が約40%いると言われています。長年飲酒して、不快にならずに飲酒できるようになった場合でも、アルコールを原因とする食道がん等のリスクが高まります。
飲酒時の注意事項
健康に配慮した飲酒の仕方
飲酒をする場合においても、様々な危険を避けるために、例えば、以下のような配慮等をすることが考えられます
①自らの飲酒状況等を把握する
②あらかじめ量を決めて飲酒をする
③飲酒前または飲酒中に食事をとる
④飲酒の合間に水を飲むなど、アルコールをゆっくり分解・吸収できるようにする
⑤一週間のうち、飲酒をしない日を設ける
避けるべき飲酒
①一時多量飲酒
一時多量飲酒(1回の飲酒機会でアルコール摂取量60g以上)は、様々な身体疾患の発症や急性アルコール中毒を引き起こす可能性があります。
②他人への飲酒の強要
リスクのある飲酒を他人に無理に勧めないようにしましょう。
③不安や不眠を解消するための飲酒
不安解消のための飲酒により依存症になる可能性を高める、飲酒により眠りが浅くなり睡眠リズムを乱す等の支障をきたすことがあります。
④病気等療養中の飲酒や服薬後の飲酒
病気等の療養中は、過度な飲酒で免疫力がより低下し、感染症にかかりやすくなる等の可能性があります。また、服薬後に飲酒した場合は、薬の効果低減や副作用が生じることがあります。
⑤飲酒中または飲酒後における運動や入浴
飲酒により血圧の変動が高まり、心筋梗塞などを引き起こす可能性があります。