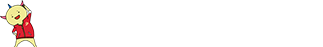女性のライフステージ
女性は思春期、成熟期、更年期、老年期とそのホルモン状況によって、また結婚や出産、育児などのライフステージによって男性とは異なったこころと体の変化があります。

出典:母性健康管理等推進支援事業事務局「働く女性の心とからだの応援サイト」
思春期
8、9歳から17、18歳頃までの間をさし、初潮を経て月経周期がほぼ順調になるまでの期間を言います。
女性ホルモンの影響で、体つきが変わり始めます(第二次性徴)。女性ホルモンには卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)という2種類があります。この女性ホルモンにより女性特有の体つきに変化していきます。
・卵胞ホルモン:肌の潤いを保つ、骨を強くする、記憶力を高める、肥満を予防する など
・黄体ホルモン:子宮内膜や子宮筋の動きを調整する、乳腺を発育させる、食欲を促す など
思春期は、急速にこころと体が成長するため不安定になりやすい時期です。周りの目が気になりダイエットへの興味が高まったり、劣等感も感じやすかったりすることもあります。
この時期に多くみられるこころの病期として、「摂食障害」があります。特に拒食等はいのちに関わることもあるため、保護者だけでなく、時には学校など周囲の方のサポートや専門の医療機関への受診が必要な場合もあります。
健康課題
・月経トラブル(貧血、月経痛、月経不順、PMS(月経前症候群))
・拒食や過食
成熟期
18 歳頃からの、女性が性的に最も成熟する時期を指します。前期は18~37歳、後期は37~45歳と区分されており、前期は一生のうちで女性ホルモンの分泌が安定して、生理も順調で、妊娠や出産に適した時期とされています。後期では、女性ホルモンは少しずつ分泌量が低下し、体のトラブルが増えていきます。
仕事やプライベートなど多忙で生活習慣が不規則なりやすくことに加え、女性特有の疾患リスクも多い時期です。
健康課題
・月経トラブル(月経前症候群(PMS)、不正出血、月経不順、貧血 等)
・不妊、不育症
・性感染症
・悪性新生物(子宮頸がん、乳がん 等)
更年期
45 歳頃から、少しずつ女性ホルモンの分泌量が減り、閉経を迎えます。日本人女性の閉経年齢は平均50.5 歳ですが、閉経年齢は個人差が大きく、40 歳代で閉経を迎える人もいれば、最近では 60 歳近くで迎える方もいます。
女性ホルモンの分泌が乱れることで、生理周期がみだれ、ほてりやのぼせ、発汗などの「更年期障害」の症状が現れる人もいます。
この時期は、プライベートでも子育てが一段落し家族構成が変化したり、近しい人の介護をすることになったり環境が変わりこころも不安定になりやすい時期です。
健康課題
・更年期障害
・骨粗しょう症
・悪性新生物(乳がん、子宮体がん 等)
(更年期障害の主な症状)
・精神神経系の症状:頭痛、めまい、不眠、不安感、イライラ感、うつ
・血管運動神経系の症状:ほてり、動悸、息切れ、発汗、むくみ
・皮膚、分泌系の症状:のどの渇き、ドライアイ
・消化器系の症状:吐き気、下痢、便秘、胃もたれ、胸やけ
・運動器系の症状:肩こり、腰痛、肩関節、しびれ
・泌尿器・生殖器の症状:月経異常、尿失禁、性交痛
老年期
更年期を過ぎたおおむね 60 歳前後からをいいます。卵胞ホルモンの分泌が少なくなり、更年期に比べて体調が安定する方が多い傾向です。ただし、閉経以降は生活習慣病のリスクが高まったり、卵胞ホルモンの低下によりうつ症状がみられたりすることがあります。
健康課題
・骨粗しょう症、骨折
・うつ病
・生活習慣病
・悪性新生物(乳がん、大腸がん、胃がん、肺がん、子宮体がん 等)
・フレイル(※介護が必要となる一歩手前の、加齢に伴い筋力や認知機能など新進の活力が低下した虚弱状態)