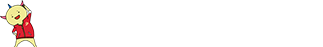睡眠と健康は密接に関係しています
睡眠には、心身の疲労を回復する働きがあり、健康を維持するために「睡眠時間の確保」と「睡眠休養感」(睡眠で休養がとれている感覚)が必要です。
睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低下したりすると、ストレスにより日常生活への支障が出るだけでなく、生活習慣病のリスクにつながり、さらにはうつ病などのこころの病の原因になることがあります。
そのため、睡眠は心身を健康に保つために非常に重要です。
睡眠障害とは
睡眠に関連した多様な病気を、まとめて「睡眠障害」と呼びます。「眠れない」だけでなく、寝付けない、途中で目が覚めたりする、睡眠中に起き上がって徘徊するなども睡眠障害に含まれます。

睡眠障害の種類
一言で睡眠障害といっても様々な種類があります。
不眠症
不眠症は、夜寝つきが悪い、眠りを維持できない、朝早く目が覚める、眠りが浅く十分眠った感じがしないなどの症状が続くことでよく眠れず、日中の眠気、注意力の散漫、疲れや様々な体調不良が起こる病気のことです。
閉塞性睡眠時無呼吸症候群
閉塞性睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に空気の通り道である気道が狭くなることによって無呼吸(10秒以上呼吸が止まること)となってしまう病気のことです。寝ている間に起こっているため自覚症状がなく病気に気づきにくいです。
日本人の500万人、成人男性の約3~7%、成人女性の約2~5%にみられると考えられていますが、適切に治療されているのはせいぜいその1割と言われています。
むずむず脚症候群
むずむず脚症候群は、じっとしているときの足の異常な感覚(むずむずする、虫が這うような感覚)を感じ、脚を動かしたりかいたりせずにはいられなくなる病気のことです。夜間に症状を感じやすい傾向があり、不眠症の原因となることがあります。日本では人口の2~7%が該当すると考えられています。
周期性四肢運動障害
周期性四肢運動障害は、睡眠中に脚や腕がピクピク繰り返し動いたり、跳ねたりすることにより、睡眠を妨げられる病気のことです。本人には自覚症状があまりありませんが、ぐっすり眠ることができず、夜間に何度も目が覚めてしまうことにより睡眠不足に陥ってしまい、昼間に強い眠気に襲われてしまうようになります。
睡眠不足症候群
慢性的な睡眠不足により生じる睡眠障害のことです。日中の眠気や疲労感、集中力の低下などの症状が現れます。
過眠症(ナルコレプシー、特発性過眠症)
夜はよく眠れているにもかかわらず、昼間の眠気が強く、仕事中に居眠りをする、 眠ってはいけない場面でも耐え難い眠気に襲われる、などの症状が続く病気のことです。
概日リズム睡眠・覚醒障害
体内時計の周期(約25時間)を外界(24時間周期)に適切に同調させることができないことで生じる睡眠障害のことです。体内時計の周期と外界の周期のずれを修正できない状態が続くと、望ましい時間に入眠・起床することができなくなっていきます。
また、無理に時間に合わせて起床しても、眠気や頭痛・倦怠感・食欲不振などの不調が現れてきます。
眠れない、眠っても休養がとれた感覚がないなどの場合、睡眠環境や生活習慣などによって生じている場合と睡眠障害によって生じている場合があります。
睡眠環境の改善などを行っても症状が改善しない場合は睡眠障害である可能性があるため、速やかに医療機関を受診しましょう。

関連リンク
厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト
不眠症 | e-ヘルスネット(厚生労働省)
昼間の眠気 -睡眠時無呼吸症候群・ナルコレプシーなどの過眠症は治療が必要 | e-ヘルスネット(厚生労働省)
睡眠・覚醒リズム障害 | e-ヘルスネット(厚生労働省)